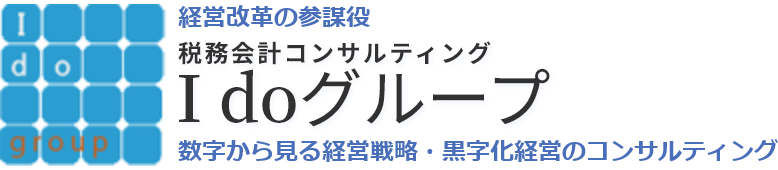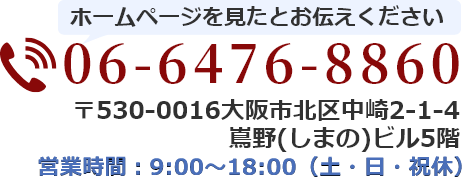ブログ
2024年12月
2024.12.18
【アシスタントブログ】2024.12.18
おはようございます。今週のメルマガ担当の吉冨です。
今年も残り2週間なので、今回はこの一年間を振り返って書いていきたいと思います。
今年は一言でいうと「成長」の一年だったように感じます。
大学の卒業論文を1か月で終わらせたこと、公認会計士を目指して勉強に明け暮れた日々、就職活動を通して自分自身を見つめ直してみたこと、社会人になる前に日本中を旅行したこと、就職したことなど、自分の中ではとても内容の濃い一年だったように思います。
「河野玄人と10時間勉強しよう」という、河野玄人さんが勉強をしている様子だけが10時間流れ続けるYouTubeをつけながら、一緒に勉強をしていたのを思い出しました。今となっては良い思い出です。
しんどいことも多々ありましたが、新しいことに挑戦することで、自分自身が成長できることを実感しました。
また、何事にも全力で挑むことで、自信をもって自分の行動を肯定できるという気付きもありました。
来年は税理士試験の勉強をするなど、さらに新たなことに挑戦していければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2024.12.18
【担当者ブログ】2024.12.18
今週のメルマガ担当の藤原です。
先日、クラウドファンディングに少額ですが、支援をいたしました。昔からファンであるバンドの方が、新たにアーティスト支援のためのスタジオを市と連携して作るというものです。市の地域振興とコミュニティづくりのための施設も併設するという、壮大な計画です。
私自身は音楽は好きですが、自分が何か演奏をした経験は全くないのですが、しっかりとレコード会社がついてくれて、音楽を作れる環境の人はやはりひとにぎりであるということを強く訴えておられました。そうした環境が整っていない人たちも音楽を続けらえる環境を提供したい。「自由に失敗で期何度でもチャレンジできる場所」づくりを目指したいともおっしゃっていました。
またその場所を地域のコミュニティにもつなげたいという思いからということでした。「商業的に成功しなければより良い設備は使えない、経済的な障壁の前に引き返す人が多い社会」という風に表現されていました。音楽がパソコンで一人で作れてしまう世の中にはなっていますが、あえてレコーディングができる環境を提供したいとというのはある種、時流に対して反対を言っているようにも感じる方もいるのかもしれませんが、そういう考え方もこの方らしいと思っています。
私自身は特に、この方に支援したという気持ちの方が正直大きいです。結果、クラウドファンディングは大幅に目標額を超えて達成されていました。そう思っている人がたくさんいたのだということが結果に出ていると思いました。
私自身もいまいちど、人と人の信頼関係や人柄について、自分を再度顧みて、感謝を忘れず伝えていけるように考えていきたいと思います。
2024.12.18
スマホアプリ納付とアクセス方法の変更
令和4年12月から国税の納付がスマホアプリで可能になりました。
スマホアプリ納付とは、GMOペイメントゲートウェイ㈱が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」から、納税者が利用可能な支払方法を選択し、納付を委託する方法のことです。
しかし、令和7年2月からは、スマホやパソコンを利用して自宅等で申告から納付までの一連の手続をデジタルで完了することを目的として、②及び③が廃止されます。
②の確定申告書等作成コーナーのQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなります。
令和6年分の所得税の納付で利用する場合は、①e-Taxからアクセスすることが必要です。
なお、スマホアプリ納付は、納付税額が30万円までの場合しか利用することができません。
30万円を超える税額の場合、複数回に分けて納付する、例えば、納付税額が100万円の場合に30万円、30万円、20万円、20万円の計4回に分けて納付するといった事例もあるようです。
30万円を超える場合、ダイレクト納付やインターネットバンキングによる電子納付など他のキャッシュレス納付手段がございます。
今回の内容は以上です。
税金もキャッシュレス決済を使った納付が増えてきました。納付書を使って窓口で納付されている方もまだ多くいらっしゃいますが、キャッシュレス決済は大変便利なので試しに使ってみてはいかがでしょうか。
2024.12.11
【アシスタントブログ】2024.12.11
最近、『理性と感情、本当に自分自身を理解していますか?』と自問しています。本日はその視点についてお話させていただきたいと思います。
理性に基づいて生きると冷淡になり、感情を表現するのが難しくなり、人間関係における感情的なコミュニケーションが困難になる可能性があります。
また、理性に過度に依存すると、実際の状況に適さない硬直した決定を下すことがあることや、共感や感情的なつながりが不足しているため周囲の人々と距離を置く傾向があることなど、常に感情をコントロールし、理性に基づいて行動することで、自分にプレッシャーをかけ、精神的なストレスや疲労を引き起こす可能性もあります。結果として、単純な喜びや豊かな生活体験を楽しむことができなくなることがあります。
過度に感情的に生きると感情に支配されすぎてしまい、合理的でない判断を下し、結果を十分に考慮せずに行動することがあります。
また、強い感情は、他人の言葉や行動によって簡単に傷つけられることを意味します。過度に感情的になることで、仕事と私生活のバランスを失い、ストレスや疲労を感じることがあります。
そのため、理性と感情のバランスを保つことが重要です。そうすれば、賢明でありながら人間味のある決定を下し、充実した意味のある生活を送ることができます。バランスの取れた幸福な生活を送るためには、理性と感情の調和を維持することが重要だと思います。
2024.12.11
【担当者ブログ】2024.12.11
12月に入り、本当に寒くなってきました。秋の季節があまりなく、夏と冬の季節の期間が長いと感じているのは私だけでしょうか。インフルエンザも流行りはじめているので、皆さまお気を付けください。
兵庫県在住のため、兵庫県知事選に選挙に行ってきたのですが、アメリカ大統領選、衆議院選挙など、SNSを駆使して選挙の情報を収集する時代になったと時代の変化を感じました。変わっていく時は一気に変化するのだと改めて実感しました。
来年の4月から娘が中学生になるのですが、ちょうどその娘が中学生2年生になるタイミングで、私の住んでいる地域では部活動がなくなることになりました。部活動がなくなるということ自体意味が分からなかったのですが、先生の働き方改革で、先生も顧問として対応できなくなっているのが要因です。
今後は地域でクラブ活動をしていくという事で、その説明会がありましたが、はじめての事なので、疑問点だらけです。これも時代の変化だなと思っておりますが、自分達は恵まれていた環境だったと、先生達に大変感謝です。
これはこれで前向きに変化を捉えて対応していきたいと思います。
経営も同じで変化はあっという間に来るので、その場で対応していくことが大切だと過去から未来につなげて考えられるようにしていきたいと思います。
2024.12.11
海外赴任者の賞与と源泉徴収
年末が近づき、冬季賞与の支給準備を始める企業も多いかと思います。
所得税法上、1年以上の予定で海外勤務が決定した従業員(海外赴任者)は、いわゆる住所の推定規定により国外居住者に該当します。国外居住者となった海外赴任者に対して、日本の会社が給与や賞与等の支払をする場合、「国内源泉所得」に該当するものについては、源泉徴収(20.42%)が必要となります。
国内源泉所得とは、国内で行った勤務に対する給与や賞与のことをいいます。そのため、日本親会社が、年の途中で海外赴任して国外居住者となった従業員に対して、国内及び国外の双方にわたって行った勤務に対して支払う給与等については、給与等支給額の総額を国内勤務日数で期間按分して、国内源泉所得を求めます。
例えば、計算期間7月から12月(国内勤務日数110日)の賞与92万円を支払う場合、国内源泉所得は以下のように計算します。
920,000円×110日(国内勤務日数)/184日(賞与の計算期間)=550,000円
したがって、国内源泉所得55万円に対して源泉徴収(20.42%の11万2,310円)が必要となります。
なお、賞与ではなく毎月の給与のように、計算期間が1か月以下のものについては、事務簡素化の観点から、給与等(全額が国内勤務対応部分である場合を除く)の計算期間の内に海外勤務期間と日本勤務期間が含まれていても源泉徴収しなくてよいという取扱いが設けられています。
今回の内容は以上です。
グローバル化に伴い日本から海外に出て働く人も増えています。日本と外国では税制が違う点が多いので、複雑な対応が求められることがしばしばあります。税制で迷うことがあれば、ぜひ税理士法人I doまでご相談ください。
2024.12.04
【アシスタントブログ】2024.12.04
すっかり夏が終わり、今年も残すところ後1ヵ月となりました。1年経つのがとても早く感じます。みなさんは今年の一年はいかがでしたでしょうか。
みなさんは、他人からどのように見られているか考えたことがありますか?
先日、僕は友人とレストランに行き店員さんに注文をしました。その様子を見ていた友人は、僕のことをとても愛想が悪いと思ったようです。別に怒っているわけでもないのですが、無表情だと怒っているように見られているようです。
笑顔を意識してみても目が笑っていないと見られ逆に怖いと言われました。他人からどう見られているか自分ではよくわからないものです。最近は、目を笑うことを意識しています。
1年もそろそろ終わるので、今年を軽く振り返りました。僕の今年の漢字を1文字で表すと「旅」です。
英語の勉強をして一人で行ったり、現地の人と英語でコミュニケーションをとりました。海外をみて自分の世界観が変わるということは全くないですが、色んな生活があるんだな、ということを学びました。貧しい地域でも小さなことに幸せを感じて生活している人々や裕福でも不満を感じて生活をする人々、とても興味深いです。お金はぶっ飛んでしまいますが一人旅は色んな事を感じて面白いものでした。
最後まで読んでいただいてありがとうございました!
2024.12.04
【担当者ブログ】2024.12.04
すっかり寒くなってコートとマフラー無しでは出かけられなくなってしまいました。
つい最近、三田のアウトレットに行ってきました。
以前にも何度か行ったのですが、今回思ったのはモノに溢れているということです。
大量の服に大量装飾品、これだけ作られているという事はそれだけ捨てられているという見方も出来ます。改めて、物を大事にする事と物を活かすという事が大切な事だと感じました。
物を大事にする、安いから買うではなく欲しいものを買う価値観で結局何も買わないまま帰路につきました。アウトレットからすると、嬉しくないお客さんだったと思いますが、見て回るのは楽しいものですね。
2024.12.04
インボイス導入2年目の消費税申告等の留意点
インボイス制度が始まり1年が経過しました。
【2割特例】令和4年分の課税売上高1,000万円超の場合は適用不可
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった事業者は、売上げに係る消費税額の2割を納付すればよい2割特例を適用できます。2割特例の適用を受ける場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は必要ありませんが、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている場合など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる場合は適用できません。
そのため、個人事業者が令和6年分の消費税の申告で2割特例を適用するには、令和4年分の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。令和4年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合、令和6年分の消費税は簡易課税又は原則課税により申告する必要があります。 なお、2割特例を適用するには、事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に適用の旨を記載するだけで適用できます。
【簡易課税】R6年12月末までの届出で6年分に適用可能なケースも
個人事業者の令和4年分の課税売上高が1,000万円を超えていて、令和6年分の消費税の申告で2割特例を適用できない場合であっても、令和4年分の課税売上高が5,000万円以下である場合は簡易課税を適用できます。 簡易課税の適用を受ける場合も2割特例と同様に、仕入税額控除のためにインボイスの保存は必要ありませんが、原則、その適用を受ける課税期間の開始日の前日までに税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
しかし、令和5年分の消費税の申告で2割特例の適用を受けた事業者については、令和6年12月31日までに届出をすることで、令和6年分の消費税の申告で簡易課税の適用を受けることができます。令和5年分の申告で2割特例の適用を受けた事業者であっても、届出が令和7年1月1日以降になると、令和6年分では簡易課税の適用を受けることができず、インボイスの保存が必要となる原則課税で消費税の申告をする必要があります。
令和6年12月17日までの登録取消届出書提出で令和7年分は免税事業者も可
令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けても、その後に登録の取消しをしたい事業者様もいることでしょう。個人事業者が令和7年からインボイス発行事業者の登録を失効させるには、令和6年12月17日までに、所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出を終えることが必要です。令和6年12月18日以降に届出をした場合、令和7年では登録は失効されずインボイス発行事業者のままとなるため、令和7年中はインボイスの交付義務が生じ、課税事業者として消費税の申告納付が必要となります。
また、インボイス発行事業者の登録を取り消しても、原則、登録日から2年間は免税事業者になることができない、いわゆる「2年縛り」が適用されます。しかし、令和5年10月1日を含む課税期間から登録している場合は、登録を取り消した翌課税期間からは、免税事業者の要件を満たしていれば、自動的に免税事業者になることができます。そのため、個人事業者が令和5年中にインボイス登録をして、令和6年12月17日までに登録取消の届出をした場合は、令和7年よりインボイス発行事業者でなくなるため、基準期間である令和5年の課税売上高が1,000万円以下であれば、令和7年は免税事業者となり、令和7年分の消費税の申告は不要となります。
令和6年以後にインボイス登録している場合は2年縛りが適用されるため、基準期間の課税売上高にかかわらず、少なくとも2年間は免税事業者になることができません。
令和6年分から12か月分の消費税を申告納付
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス登録をして課税事業者となり、令和5年に初めて消費税の申告納付を行った事業者も多いことと思います。
今回の内容は以上です。
- 1 / 1
最近のエントリー
アーカイブ
- 2025年06月(1)
- 2025年05月(1)
- 2025年01月(2)
- 2024年12月(9)
- 2024年11月(11)
- 2024年10月(6)
- 2024年01月(1)
- 2023年04月(2)
- 2023年02月(1)
- 2023年01月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年04月(1)
- 2022年01月(1)
- 2021年10月(1)
- 2021年04月(1)
- 2021年01月(1)
- 2020年01月(1)
- 2019年04月(1)
- 2019年01月(1)
- 2018年08月(1)
- 2018年04月(1)
- 2018年03月(1)
- 2018年02月(1)
- 2018年01月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(1)
- 2017年10月(1)
- 2017年09月(1)
- 2017年08月(1)
- 2017年07月(1)
- 2017年06月(1)
- 2017年05月(1)
- 2017年04月(1)
- 2017年03月(1)
- 2017年02月(1)
- 2017年01月(1)
- 2016年11月(1)
- 2016年09月(1)
- 2016年07月(1)
- 2016年05月(1)
- 2016年03月(1)
- 2016年01月(1)
- 2015年12月(1)
- 2015年10月(1)
- 2015年01月(1)
- 2014年02月(1)
- 2014年01月(1)
- 2013年01月(1)
- 2012年10月(1)
- 2012年08月(1)
- 2012年07月(1)
- 2012年06月(1)
- 2012年05月(1)
- 2012年04月(1)
- 2012年03月(1)
- 2012年02月(1)
- 2012年01月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年09月(1)
- 2011年08月(1)
- 2011年07月(1)
- 2011年06月(1)
- 2011年05月(1)
- 2011年04月(1)
- 2011年03月(1)
- 2011年02月(1)
- 2011年01月(1)
- 2010年12月(1)
- 2010年11月(1)
- 2010年10月(1)
- 2010年09月(1)
- 2010年08月(1)
- 2010年07月(1)
- 2010年06月(1)
- 2010年05月(1)
- 2010年04月(1)
- 2010年03月(1)
- 2010年02月(1)
- 2010年01月(1)
- 2009年12月(1)
- 2009年11月(1)
- 2009年10月(1)
- 2009年09月(2)
- 2009年08月(1)
- 2009年07月(1)
- 2009年06月(1)
- 2009年05月(1)
- 2009年03月(1)
- 2009年02月(1)
- 2009年01月(1)
- 2008年12月(1)
- 2008年11月(1)
- 2008年09月(1)
- 2008年08月(2)
- 2008年07月(1)
- 2008年06月(1)
- 2008年05月(1)
- 2008年04月(1)
- 2008年03月(2)
- 2008年01月(1)
- 2007年12月(1)
- 2007年11月(1)
- 2007年10月(1)
- 2007年08月(1)
- 2007年07月(1)
- 2007年06月(1)
- 2007年05月(1)
- 2007年04月(1)
- 2007年03月(1)
- 2007年02月(1)
- 2007年01月(1)
- 2006年12月(1)
- 2006年10月(1)
- 2006年09月(1)
- 2006年08月(1)
- 2006年07月(1)
- 2006年06月(1)
- 2006年05月(1)
- 2006年04月(1)
- 2006年03月(1)
- 2006年02月(1)
- 2006年01月(1)
- 2005年11月(2)
- 2005年10月(1)
- 2005年09月(2)
- 2005年08月(1)
- 2005年07月(1)
- 2005年06月(1)
- 2005年05月(1)
- 2005年04月(1)
- 2005年03月(1)
- 2005年02月(1)
- 2005年01月(1)
- 2004年12月(2)
- 2004年11月(1)
- 2004年10月(1)